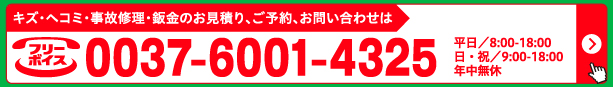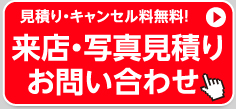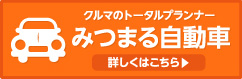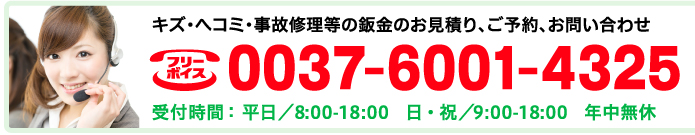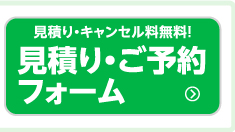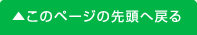- DIYでできるバンパー修理と注意点[2025.07.29]
-
諦めていたバンパーの傷、DIYで解決できるかもしれません!
車のバンパーにできてしまった傷やヘコミ。見るたびにため息が出てしまうものの、修理費用を考えると二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、実はバンパーの傷やヘコミは、その種類や程度によってはDIYで修理することが可能です。この記事を読めば、ご自身の車のバンパーの状態を見極め、適切な修理方法を選択できるようになるでしょう。DIYのメリット・デメリットを理解し、安全かつ満足のいく仕上がりを目指しましょう。
目次
1.DIYで修理できるバンパーの傷やヘコミとは?
2. バンパーのタッチペン補修方法
3. スプレー塗装での補修手順とコツ
4. バンパーの軽いヘコミを修理する方法
5. パテを使ったバンパー修理の基本
6. 失敗しないためのマスキングテクニック
7. DIY修理の仕上がりとプロ修理の違い
8. クリアコートを使った仕上げのポイント
9. バンパー修理後のメンテナンス方法
10. DIYで修理すべきでないバンパーの状態とは?1. DIYで修理できるバンパーの傷やヘコミとは?
車のバンパーにできた傷やヘコミは、見た目を損なうだけでなく、放置するとサビの発生やさらなる破損につながる可能性もあります。しかし、すべての傷やヘコミが専門業者による大規模な修理を必要とするわけではありません。DIYで修理できるバンパーの傷やヘコミには、いくつかの特徴があります。
まず、「軽度の擦り傷」が挙げられます。これは、バンパーの表面にごく浅くついた傷で、塗装のクリア層や上塗り塗料の最上層に限定されていることが多いです。爪でなぞっても引っかかりを感じない程度の傷であれば、DIYでの修復が比較的容易です。この種の傷は、コンパウンド磨きやタッチアップペンで目立たなくすることが可能です。
次に、「ごく小さな塗装剥がれ」もDIYでの対応が可能な場合があります。飛び石などで点状に塗装が剥がれてしまったようなケースで、その範囲が数ミリ程度であれば、タッチアップペンで色を補うことができます。重要なのは、塗装剥がれが下地まで達しておらず、バンパー本体の素材が露出していないことです。
DIYでの修理を検討する際は、まずご自身の車のバンパーの状態を正確に把握することが重要です。傷の深さ、範囲、ヘコミの程度、そしてバンパーの素材や構造をよく観察し、無理のない範囲で挑戦するようにしましょう。
2. バンパーのタッチペン補修方法
タッチペン補修は、主に軽度の擦り傷やごく小さな塗装剥がれに適しており、費用を抑えつつ目立たなくさせたい場合に有効な方法です。
まず、正確なボディカラーのタッチペンを用意することが最も重要です。車種や年式によって同じ「白」でも微妙に色が異なるため、車のカラーコードを確認し、それに合致する製品を選びましょう。
次に、傷の周辺を清掃します。砂やホコリ、油分などが付着していると、塗料の密着が悪くなり、仕上がりに影響が出ます。中性洗剤と水で丁寧に洗い、乾燥させたら、シリコンオフなどの脱脂剤で完全に油分を取り除きましょう。
準備が整ったら、いよいよ補修作業に入ります。
- 傷の確認と下処理:
- 傷の深さを確認し、もし塗装面が盛り上がっている場合は、細目の耐水ペーパーで軽く研磨して平滑にします。ただし、研磨しすぎるとかえって傷が広がる可能性があるので注意が必要です。
- タッチペンの塗布:
- タッチペンをよく振って塗料を均一にします。
- 付属の筆や、より細かな作業には細い面相筆などを使用し、傷の部分に少量ずつ塗料を乗せていきます。
- 塗装面よりやや盛り上がる程度まで塗布することで、乾燥後の研磨で平滑にすることができます。
- 塗料が完全に乾燥するまで、車種や気温にもよりますが、数時間から半日程度は触らないようにしましょう。
- 研磨と仕上げ:
- 塗料が完全に乾燥したら、必要に応じてコンパウンドで研磨し、周囲の塗装面との段差をなじませます。
- 粗目のコンパウンドから始め、徐々に細目のコンパウンドへと移行することで、ツヤを出すことができます。
- ワックスやコーティング剤を塗布して保護することで、より美しい仕上がりを保てます。
タッチペン補修は、「目立たなくする」ことが目的であり、完璧な仕上がりを求める場合は専門業者への依頼が賢明です。
3. スプレー塗装での補修手順とコツ
バンパーの比較的広範囲な擦り傷や、タッチペンでは対応しきれないような範囲の塗装剥がれには、スプレー塗装が有効です。プロのような完璧な仕上がりは難しいものの、適切な手順とコツを抑えれば、DIYでもかなりきれいに補修することが可能です。
スプレー塗装を始める前に、作業環境の確保が重要です。風のない日を選び、ホコリが舞いにくい場所で行いましょう。
必要な道具としては、ボディカラーに合ったカラースプレー、クリアスプレー、プライマー、パテ、耐水ペーパー、脱脂剤、マスキングテープ、マスキングシート、新聞紙、コンパウンドなどがあります。
スプレー塗装の基本的な手順は以下の通りです。
- 下準備と清掃:
- 補修箇所の周囲を、中性洗剤と水で丁寧に洗い、完全に乾燥させます。
- 次に、シリコンオフなどの脱脂剤で油分を完全に除去します。
- 必要に応じてパテで凹凸を修正し、乾燥後に耐水ペーパーで平滑に研磨します。
- 塗装面以外に塗料が付着しないよう、マスキングテープとマスキングシート、新聞紙などを用いて丁寧にマスキングします。
- プライマーの塗布:
- プラスチックバンパーの場合は、必ずプラスチック用プライマーを塗布します。
- スプレー缶をよく振り、対象から20〜30cm程度離して、薄く均一にスプレーします。
- プライマーが完全に乾燥するまで待ちます。
- カラースプレーの塗布:
- カラースプレーをよく振り、同様に20〜30cm離して、薄く均一にスプレーします。
- 一度に広い範囲を塗ろうとせず、少しずつ重ね塗りを繰り返します。
- 隣接する未塗装部分との境目をぼかすように、「ぼかし塗装」を意識してスプレーします。
- 各層が乾燥するのを待ち、完全に色が乗るまで重ね塗りを繰り返します。
- クリアスプレーの塗布:
- カラースプレーが完全に乾燥したら、クリアスプレーを塗布します。
- カラースプレーと同様に、薄く均一に重ね塗りします。
- クリア層が完全に乾燥するまで、十分な時間を置きます。
- 仕上げ:
- クリア層が完全に乾燥したら、マスキングを剥がします。
- 細目のコンパウンドで塗装面を軽く磨き、ツヤ出しと周囲とのなじませを行います。
- ワックスやコーティング剤を塗布して保護します。
スプレー塗装は、天候の良い日を選び、時間に余裕を持って作業することが重要です。
🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗
小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト
4. バンパーの軽いヘコミを修理する方法
車のバンパーにできてしまった軽いヘコミは、素材が樹脂製である特性を利用して、比較的簡単にDIYで修理できる場合があります。
バンパーの軽いヘコミ修理に必要な道具は、主にドライヤーやヒートガン、軍手や厚手のゴム手袋、場合によっては内張り剥がしなどの工具です。
ヘコミ修理の基本的な手順は以下の通りです。
- ヘコミ箇所の清掃:
- まず、ヘコミの周辺を中性洗剤で丁寧に洗い、砂や泥などの汚れを完全に除去します。
- ヘコミの内側からのアプローチ:
- もしバンパーの裏側からヘコミにアクセスできる場合は、その方が作業が容易で、仕上がりもきれいになりやすいです。
- バンパーを固定しているクリップやネジを外し、必要であればバンパーの一部または全体を取り外します。
- 熱を加えて変形を戻す:
- ドライヤーやヒートガンを使い、ヘコミのある部分をゆっくりと温めます。
- 注意点: 熱しすぎるとバンパーの素材が溶けたり、変色したりする可能性があるので、適切な距離を保ち、触って熱さを確認しながら作業を進めます。
- バンパーが十分に温まり、素材が柔らかくなってきたら、ヘコミの裏側から手や指でゆっくりと押し出します。
- 一気に押し出そうとせず、少しずつ力を加えて形状を戻していくのがコツです。
- 元の形状に戻ったら、急激に冷やさず、自然に冷めるのを待ちます。
- 仕上げ:
- ヘコミが直ったら、修理箇所の状態を確認します。
- バンパーを取り外した場合は元に戻し、全体の清掃を行います。
この方法は、比較的浅く、バンパーの素材が伸びていないヘコミに特に効果的です。
5. パテを使ったバンパー修理の基本
バンパーにできた比較的深い傷や、熱で戻しきれないようなヘコミ、またはわずかな欠損がある場合、パテを使った修理が有効です。
パテの種類:バンパー修理で主に使用されるパテは、大きく分けて以下の2種類です。
- ポリエステルパテ: 主に深い傷やヘコミ、大きな凹凸の修正に使用されます。硬化剤と混ぜて使用する2液性で、硬化が早く、研磨性にも優れています。
- ポリパテ: 比較的小さな傷や凹凸の修正、またはポリエステルパテの後の仕上げに使用されます。
傷の深さや範囲に応じて、適切な種類のパテを選択することが重要です。
パテ修理の基本的な手順は以下の通りです。
- 下準備と清掃:
- 修理箇所の汚れを中性洗剤で丁寧に洗い流し、完全に乾燥させます。
- シリコンオフなどの脱脂剤で油分を完全に除去します。
- 傷やヘコミの周辺の塗装面を、粗目の耐水ペーパーで研磨し、塗料の密着性を高めます。
- 必要に応じて、作業箇所以外にパテが付着しないよう、マスキングを行います。
- プライマーの塗布:
- プラスチック素材のバンパーの場合、パテの密着性を高めるために、プラスチック用プライマーを薄くスプレーします。
- パテの練り合わせと塗布:
- 2液性のパテを使用する場合、主剤と硬化剤を規定の割合で練り合わせます。
- 練り合わせたパテを、パテ板やヘラにとって、傷やヘコミの部分に均一に塗布します。
- 一度に厚塗りせず、薄く伸ばすように塗布し、必要に応じて重ね塗りをします。
- パテを盛り付けすぎると、乾燥後の研磨に手間がかかるため、できるだけ平らに、対象の凹凸を埋めるように塗布するのがコツです。
- パテの乾燥:
- パテが完全に硬化するまで、十分な時間を置きます。硬化時間はパテの種類や気温によって異なりますが、焦らず待つことが重要です。
- 研磨:
- パテが完全に硬化したら、耐水ペーパーを使って研磨し、平滑な面を作り出します。
- 最初は粗目の耐水ペーパーで大まかに研磨し、徐々に番手を上げてきめ細かく仕上げていきます。
- 研磨の際は、広い範囲を均一に研磨するよう心がけ、周囲の塗装面との段差がなくなるように丁寧に作業します。
- 指で触って、凹凸がないか、平滑になっているかを何度も確認します。
- 最終確認と清掃:
- 研磨が完了したら、パテ粉をきれいに拭き取り、再度脱脂を行います。
- この状態で、塗装に移行できる状態になっているか最終確認します。
パテ作業は、その後の塗装の仕上がりを左右する非常に重要な工程です。
6. 失敗しないためのマスキングテクニック
車の修理におけるマスキングは、塗装やパテ作業において、意図しない場所に塗料やパテが付着するのを防ぎ、美しい仕上がりを実現するために不可欠な工程です。
失敗しないためのマスキングテクニックには、いくつかの重要なポイントがあります。
- マスキングテープとマスキングシートの選択:
- マスキングテープ: 塗料が染み込みにくい、粘着力が強すぎず剥がしやすい自動車補修用マスキングテープを選びましょう。
- マスキングシート/新聞紙: 広範囲を覆うために使用します。塗料が透過しない厚手のものや、あらかじめテープが一体になったものも便利です。
- 下準備の徹底:
- マスキングする部分を、完全に清潔にしておきましょう。ホコリや油分が付着していると、テープの粘着力が低下し、作業中に剥がれてしまう可能性があります。
- テープを貼る前に、指で軽く触って、水分や油分が残っていないか確認します。
- 境目を意識した貼り方:
- 塗装面とマスキングする面の境目を、できる限り直線になるように丁寧に貼っていきます。
- 「ぼかし塗装」を行う場合は、塗装範囲のギリギリにテープを貼るのではなく、塗装したい範囲よりも少し広めにテープを貼り、塗装の境目をわざとぼかすようにマスキングを行います。
- 隙間を作らない貼り方:
- マスキングテープを貼る際は、テープの下に空気が入らないように、指やヘラを使ってしっかりと押さえつけます。
- テープ同士が重なる部分は、しっかりと密着させ、塗料が入り込まないようにします。
- パーツの隙間やドアのゴムパッキンの裏側など、塗料が回り込んで欲しくない場所は、細いテープや、より薄いシートを差し込むようにして保護します。
- 広範囲の養生:
- 塗装したい箇所以外は、広範囲にわたってマスキングシートや新聞紙でしっかりと覆います。
- 風のある屋外での作業は、シートがめくれないように、テープでしっかりと固定したり、重りを置いたりする工夫が必要です。
- 剥がすタイミングと注意点:
- 塗料が完全に乾燥する前にマスキングテープを剥がすと、塗料が伸びてしまったり、塗装面が崩れてしまったりする可能性があります。
- しかし、完全に乾燥しすぎてから剥がすと、テープが塗料と一緒に固まってしまい、きれいに剥がせなかったり、塗料の端がギザギザになったりすることがあります。
- 剥がす際は、塗装面に対して90度に近い角度で、ゆっくりと均一な力で剥がしていくと、塗料の端がきれいに仕上がります。
マスキングは地味な作業ですが、その出来栄えが最終的な仕上がりに大きく影響します。
🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗
小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト
7. DIY修理の仕上がりとプロ修理の違い
バンパーの傷やヘコミをDIYで修理する場合と、プロの業者に依頼する場合では、その仕上がりには明確な違いが生じます。
DIY修理の仕上がり:DIY修理の最大の魅力は、やはりコストを抑えられる点にあります。材料費のみで済むため、数千円から数万円程度で修理が可能です。
- 色の再現性: 市販のタッチペンやカラースプレーでは、車の純正色と完全に一致させるのは非常に困難です。
- 塗装の均一性: スプレー塗装の場合、プロのような均一な膜厚で塗装するのは熟練の技を要します。
- 下地の処理: パテを使った修理の場合、研磨の技術が仕上がりに直結します。
- 耐久性: DIYでの塗装は、プロの設備や技術に比べて塗料の密着性や耐久性が劣る場合があります。
総じて、DIY修理は「目立たなくする」ことを目的とするには十分ですが、「完全に元通りにする」ことや「新車のような輝きを取り戻す」ことは、非常に難しいと言えます。
プロ修理の仕上がり:一方、プロの業者に修理を依頼する場合、その仕上がりは格段に向上します。
- 完璧な色合わせ: 専門業者は、塗料メーカーの配合データや独自の調色技術を駆使し、車種や年式、経年劣化まで考慮した上で、最も近い色を調色します。
- 均一で滑らかな塗装面: 専門の塗装ブースや高性能なスプレーガンを使用し、最適な環境下で熟練の職人が塗装を行うため、液だれやムラがなく、均一で美しい光沢のある塗装面を実現します。
- 徹底した下地処理: パテ処理から研磨、サフェーサーの塗布まで、専門的な知識と技術に基づき、徹底的に下地を整えます。
- 高い耐久性: プロが使用する塗料は、耐久性や耐候性に優れており、適切な下地処理と乾燥工程を経て塗装されるため、長期間にわたって美しい状態を保ちます。
- 保証と安心感: 多くの修理工場では、修理後の保証が付帯しており、万が一の不具合が発生した場合でも安心です。
特に、売却を考えている車や、細部にまでこだわりたい方には、プロへの依頼が最善の選択肢となるでしょう。
8. クリアコートを使った仕上げのポイント
バンパーの塗装修理において、クリアコートは、単にツヤを出すためだけの存在ではありません。塗装面を保護し、耐久性を高め、そして何よりも最終的な仕上がりの美しさを大きく左右する重要な役割を担っています。
クリアコートを使った仕上げのポイントは以下の通りです。
- クリアコートの選択:市販のクリアスプレーには、アクリル系のものとウレタン系のものがあります。
- アクリル系クリア: 比較的安価で手軽に扱えますが、乾燥後の塗膜が柔らかく、耐久性や耐候性がウレタン系に劣ります。
- ウレタン系クリア: 主剤と硬化剤を混ぜて使用するタイプで、硬化後の塗膜が非常に硬く、ガソリンや溶剤に強く、耐久性や耐候性、光沢に優れています。
- 適切なタイミングでの塗布:
- カラー塗料が完全に乾燥する前にクリアコートを塗布すると、色の層がにじんでしまったり、ムラが生じたりする可能性があります。
- 理想は、カラー塗料が「指触乾燥」した状態、つまり触っても指紋がつかない程度に乾燥しているが、まだ完全に硬化しきっていないタイミングです。
- 薄く、均一に重ね塗り:
- クリアコートもカラースプレーと同様に、一度に厚塗りすると液だれの原因となります。
- 対象物から20〜30cm程度離し、薄く、均一にスプレーします。
- スプレーを常に動かし続けることが重要です。
- 1回塗布したら数分間乾燥させ、塗料が半乾きの状態になったら次の層を重ねていきます。
- 特に最終層は、ムラなく全体を覆うように、滑らかな動きでスプレーするよう心がけましょう。
- 「肌」の形成と光沢:
- プロの塗装では、塗料の表面にわずかな凹凸が形成され、それが光を乱反射して独特のツヤを生み出します。
- クリアコートの最終層は、少し多めに、しかし液だれしない程度に塗布することで、より深いツヤを出すことができます。
- 研磨と磨き:
- クリアコートが完全に乾燥したら、必要に応じて研磨と磨きを行います。
- 細目の耐水ペーパーで軽く水研ぎし、表面のザラつきや小さなホコリを取り除きます。
- 次に、粗目のコンパウンドから始め、徐々に細目のコンパウンドへと移行しながら、丁寧に磨き上げます。
- 最後に、液体ワックスやコーティング剤で保護し、美しい輝きを長持ちさせましょう。
焦らず、段階を踏んで作業することが、満足のいく仕上がりへの近道です。
9. バンパー修理後のメンテナンス方法
DIYでバンパーの傷やヘコミを修理した後、その美しい仕上がりを長持ちさせるためには、適切なメンテナンスが不可欠です。
バンパー修理後のメンテナンスは、主に以下の点に注意して行いましょう。
- 修理後の初期保護:
- 修理が完了し、塗装やクリアコートが完全に乾燥・硬化した後、すぐに洗車機にかけるのは避けましょう。
- 可能であれば、修理後すぐにワックスやガラス系コーティング剤を塗布して、塗装面を保護することをお勧めします。
- 定期的な洗車と清掃:
- 定期的に洗車を行い、砂や泥、鳥の糞、虫の死骸などの汚れを洗い流しましょう。
- 特に、鳥の糞や樹液などは酸性度が高く、塗装面を侵食する可能性があるため、見つけたらすぐに洗い流すようにしましょう。
- 洗車の際は、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロスを使用し、力を入れすぎないように優しく洗うのがポイントです。
- ワックスやコーティングの定期的な施工:
- ワックスやコーティング剤は、塗装面を物理的に保護し、ツヤを維持する上で非常に有効です。
- 使用する製品の推奨頻度にもよりますが、数ヶ月に一度程度のペースで定期的に施工することをお勧めします。
- 特にDIYで補修した箇所は、プロの塗装に比べて耐久性が劣る可能性があるため、より一層の注意を払って保護しましょう。
- 撥水性の高い製品を選ぶことで、雨水が塗装面に留まるのを防ぎ、水アカの発生を抑える効果も期待できます。
- 直射日光や高温からの保護:
- 可能であれば、屋根付きの駐車場に駐車したり、ボディカバーを使用したりして、直射日光に当たる時間を減らす工夫をしましょう。
- 夏場の炎天下など、高温になる場所での駐車も、塗装に負担をかける可能性があります。
- 飛び石や新たな傷への対処:
- 運転中に飛び石などで新たな小さな傷がついてしまった場合は、放置せずに早めにタッチペンなどで補修しましょう。
手間を惜しまず、愛車を大切にケアしていく姿勢が、満足のいく結果につながるでしょう。
🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗
小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト
10. DIYで修理すべきでないバンパーの状態とは?
これまでにDIYでバンパーの傷やヘコミを修理する方法について解説してきましたが、すべてのバンパーの損傷がDIYで対応できるわけではありません。
DIYで修理すべきでないバンパーの状態は以下の通りです。
- バンパー本体に亀裂や穴が開いている場合:
- プラスチック製のバンパーに亀裂が入っている場合や、穴が開いてしまっている場合は、単純なパテや塗装だけでは完全に強度を回復させることは困難です。
- バンパーが大きく変形している場合:
- 熱を加えても元に戻らないような、広範囲にわたる大きなヘコミや、バンパー全体がねじれているような変形は、DIYでは修正が非常に困難です。
- バンパーの取り付け部分が歪んでいる場合も、正確に取り付けることができず、見栄えが悪くなるだけでなく、走行中にガタつきが生じることもあります。
- センサーやカメラなどの部品が損傷している場合:
- 最近の車には、衝突回避支援システムやパーキングアシスト機能のために、バンパー内部に各種センサーやカメラが組み込まれていることが多くあります。
- これらの部品が損傷している、または損傷している可能性がある場合は、DIYでの修理は絶対に避けるべきです。
- バンパーの取り付け部分や内部構造に影響が出ている場合:
- バンパーを固定しているブラケットが破損している、または車体側のフレームや骨格にまで影響が及んでいる場合は、バンパーだけの修理では解決しません。
- これは、衝突安全性に直結する問題であり、専門業者による点検と修理が必須となります。
- 塗装が広範囲にわたり剥がれている、または下地が露出している場合:
- 広範囲にわたって塗装が剥がれ、下地の樹脂や金属が露出している状態は、DIYでのスプレー塗装では完璧な仕上がりを得るのが非常に難しいです。
- 完璧な仕上がりを求める場合:
- 「新車のような完璧な仕上がり」や「売却時に高評価を得たい」といった高いクオリティを求める場合は、迷わずプロの業者に依頼すべきです。
DIY修理は、あくまでも軽度の損傷を目立たなくさせるための手段であり、車の安全性や機能性、そしてご自身の安全を最優先に考えるべきです。少しでも不安を感じたり、判断に迷うような損傷の場合は、自己判断せずに、自動車修理の専門業者に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
完璧な仕上がりを目指すDIY修理の総括と安全への配慮
車のバンパーにできた傷やヘコミは、その種類や程度によってはDIYで修理することが可能です。本記事では、DIYで修理できるバンパーの傷やヘコミの見極め方から、タッチペンやスプレー塗装、パテを使った具体的な補修方法、ヘコミの修理方法、マスキングのテクニック、クリアコートによる仕上げのポイントまで、詳細に解説してきました。
DIY修理の最大のメリットは、コストを抑えつつ、気になる傷やヘコミを目立たなくできる点にあります。しかし、色の再現性や塗装の均一性、耐久性といった面では、プロの修理には及ばないことを理解しておく必要があります。
DIYでバンパー修理に挑戦する際は、焦らず、丁寧な下準備と作業を心がけることが成功への鍵となります。正しい知識と適切なツールを使用し、ご自身の車の状態を正確に判断した上で、無理のない範囲で挑戦しましょう。そして、修理後は定期的なメンテナンスを行い、美しい仕上がりを長持ちさせることも忘れてはなりません。
🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗
小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト
- 傷の確認と下処理: